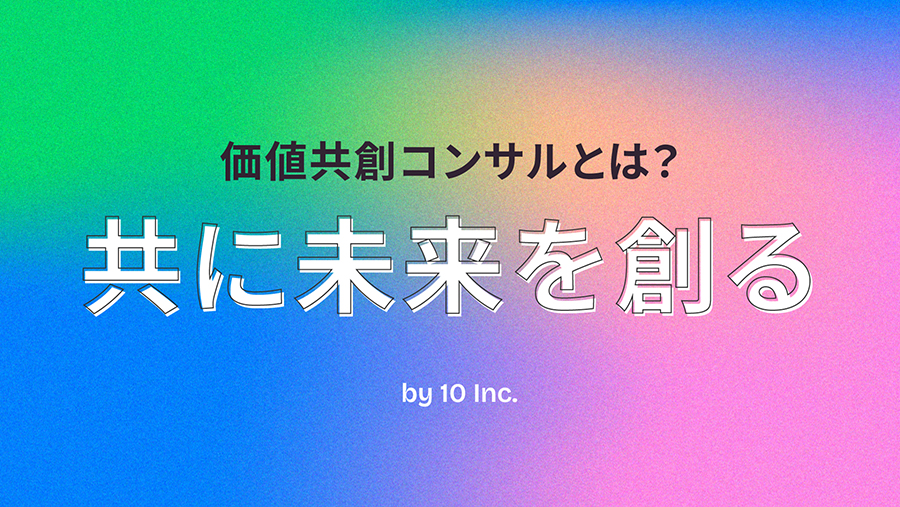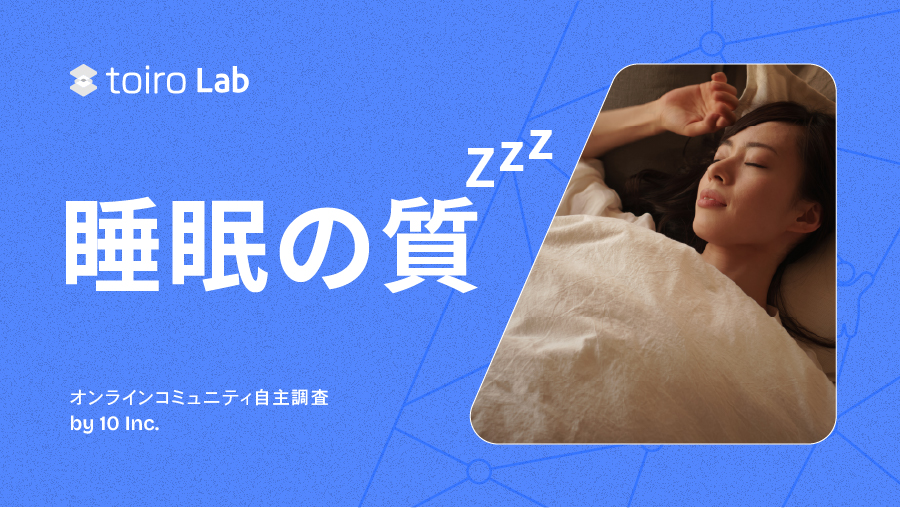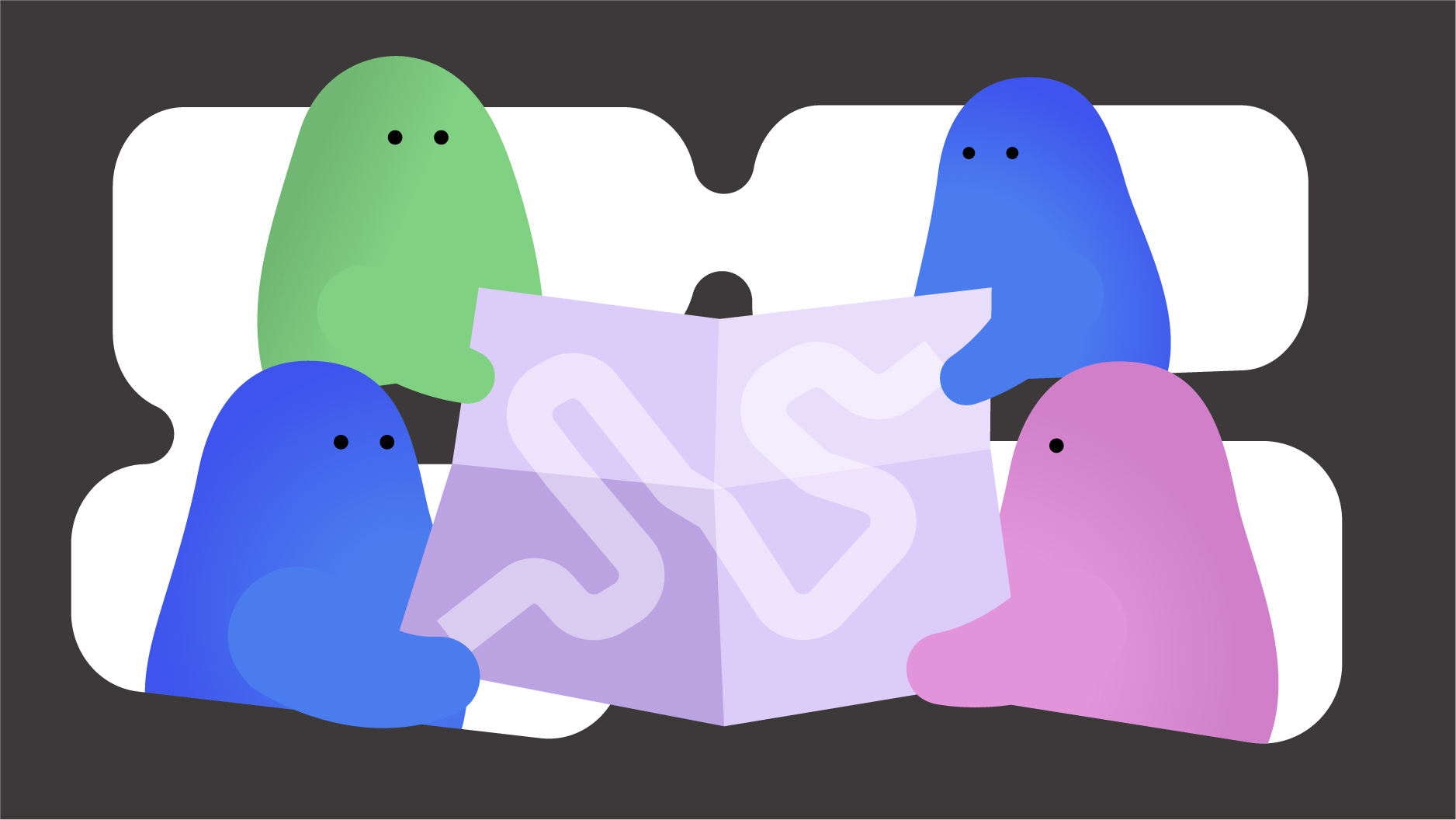AIは共創のパートナーになれるか?― 人とAIで“まだ見ぬ価値”をつくる
2025.8.19
こんにちは、10 Inc. PRです。
前回のコラム「異なるからこそ、つながれる ― 多様性が拓く共創の未来」では、価値共創における“多様性”の意義について考察しました。今回は、AIという存在が、私たちヒトの“共創のパートナー”になり得るのか?というテーマを深掘りしてみたいと思います。
生成AIの登場により、情報収集やアイデア創出、分析スピードは飛躍的に向上し、私たちの働き方や思考プロセスは日々アップデートされています。そんな中、「AIと価値を共創する」という視点は、もはや未来の話ではなく、すでに現場に根を張りはじめています。
なぜ、いま「価値共創」なのか?
これまでのビジネスは「価値を提供する企業」と「それを受け取る顧客」という一方向的な関係が前提でした。しかし現代は、価値観が多様化し、社会全体が「正解の不在」の時代を生きています。
そんな中で、生活者とともに価値をつくっていく『価値共創』の考え方は、ますます重要性を増しています。
私たちが行っているマーケティングリサーチの現場でも、“まだ言語化されていない価値”を、生活者とともに見つけ出していくようなプロジェクトが増えています。
つまり、価値共創とは、ヒトの中に眠っている“まだ形になっていないもの”を、対話や体験を通じて発見し、育てていくプロセスだと捉えています。そしてそのプロセスに、AIはどう関われるのでしょうか?
AIとの“対話”が開く、思考の回路
生成AIは、文章・画像・音声など多様なアウトプットを生み出せる存在へと進化しています。中でも、ChatGPTのようなツールとの“対話”は、私たちの思考を刺激し、新しい視点をもたらしてくれます。
実際に私たちも、ブレストやコンセプト設計の初期段階でAIに問いを投げてみることがあります。たとえば、
- 「生活者が●●に求めている“体験価値”は?」
- 「この商品アイデアを、ペルソナ目線で語るとどうなる?」
といった質問を投げることで、私たちの仮説を揺さぶるような、意外な視点が返ってきます。
ここで重要なのは、「AIがすごい」のではなく、「AIにどんな問いを立てるか」「どう使いこなすか」によって、返ってくるアウトプットの質が大きく変わるという点です。
AIは“使い手の鏡”でもあり、その知性や感性、構造的な思考力がアウトプットの質にそのまま跳ね返ってきます。つまり、AIの価値を引き出せるかどうかは、私たち次第なのです。
だからこそ、AIとの対話は、自分の思考のクセや前提を見直すチャンスでもあります。問い直し、視点をずらし、仮説を深める――そんな思考の回路を開いてくれる存在として、AIは「共創の入り口」に立っているのではないかと、感じています。
リサーチにおけるAIの“共創性”
マーケティングリサーチの現場においても、AIはすでに「共創の相棒」としての存在感を増しています。とくに以下の領域では、AIの力が大いに発揮されています。
テキストマイニングの自動化
大量の自由回答からキーワードや傾向を高速に抽出
生活者の声の要約・分類
多様な意見の中にある意味のまとまりを可視化
統計分析の効率化・高度化
大量データから相関や傾向を迅速に把握し、より精緻な仮説構築を支援
さらに、当社が開発したMROC専用プラットフォーム「MindSquare™」には、
回答者の発言をAIが自動で要約・抽出・アフターコーディングできる機能を搭載しています。
これにより、定性データの分析においても、これまで人手で膨大な時間をかけていた作業が圧倒的に効率化されました。
こうしたAIの活用によって、ヒトは「問いの設計」「仮説の構築」「解釈と提案」など、より創造的な領域に集中できるようになります。
AIは“正解”を出す存在ではなく、“問いの解像度”を高めてくれる存在。
この関係性こそ、リサーチの未来を支えるものだと、私たちは考えています。
AIの限界と、“拡張”としての未来
もちろん、AIにも限界はあります。たとえば、
- 生活者の「違和感」や「引っかかり」といった感情の微細なニュアンス
- 対話の空気感や場の温度、タイミングに流れる空気
といった、暗黙知に近い情報を読み取るのは、今のAIには難しい領域です。
しかしここで問うべきは、「AIはヒトを代替する存在なのか?」ではなく、「AIがいかにしてヒトの能力を拡張できるか?」という視点です。
近年の研究では、人間とAIがそれぞれ予測や判断を行い、その結果を統合する“アンサンブル”の効果に注目が集まっています。
ヒトとAIは異なる思考パターンを持ち、それぞれに得意・不得意があります。ヒトは直感や文脈理解に長けていますが、膨大なデータには弱い。AIはその逆です。この“違い”を組み合わせることで、精度の高い判断や新しい発見につながる。つまり、「違うからこそ、価値が生まれる」共創の関係が築けるのです。
AIは“共創の触媒”である
私たちは、AIを「ヒトの代わり」ではなく、「ヒトの問いを深めるパートナー」「共創の触媒」として捉えています。AIとの対話を通じて、私たちは思考を深め、想像を広げ、未来をかたちづくる新たな価値の種を見つけることができます。ビジネスの現場では、生成AIを使って創造的なアイデアを生み出したり、戦略の妥当性を評価したりする試みも進んでいます。
これからは、「AIとどう共創するか」が、仕事の質を左右する時代になるでしょう。
次回のコラムでは、「CX × 価値共創」をテーマに発信したいと思います。
顧客体験(CX)がますます重視されるいま、生活者との共創によってどのように価値を育てていけるのか考察していきたいと思います。