異なるからこそ、つながれる ― 多様性が拓く共創の未来
2025.7.18
こんにちは、10 Inc. PRです。
今回のコラムは、当社が「価値共創」というプロセスをコアにお仕事をさせて頂いている中で、新たな視点を持っていただけたらと思い記事にしてアーカイブしていきたいと思います。
「違いがあるからこそ、つながれる」
この言葉が、今のビジネスにおいてますます重要な意味を持つようになっています。市場の変化が激しく、正解がひとつではない時代。企業が生き残るためには、社内外の多様な視点を活かし、共に価値を創る“共創力”が不可欠です。
本記事では、多様性が共創を促す理由と、私たち企業がそれをどう活かしていけるかを考えてみます。
多様性は「分断」ではなく「つながり」の起点
多様性(Diversity)という言葉は、時に「違いによる分断」や「摩擦」を連想させるかもしれません。しかし、実際には違いがあるからこそ、対話が生まれ、共通の目的が見つかります。
海外に住むと強く実感することですが、日本国内においても、世代・職種・価値観の違う人々と関わる中で「違い」を感じる機会は少なくありません。こうした違いが交差すると、これまで見えていなかった課題や可能性が浮かび上がってきます。
そして、その違いを乗り越えるプロセスこそが、組織の信頼を育み、強いチームをつくるのです。
共創とは何か?協働との違い
「共創(Co-Creation)」は、単なる協力や分業とは異なります。それは、異なる立場や視点を持つ人々が出会い、対話し、交流しながら新しい価値を生み出す創造的な営みです。
「協働」が役割分担による効率化を目的とするのに対し、「共創」は違いを尊重しながらゼロから価値を生み出す過程。そこには、摩擦もあれば、驚きもある。その掛け合わせからこそ、イノベーションは生まれるのです。
異なる視点が生むイノベーション
多様性がイノベーションの源泉であることは、数多くの研究や実例が示しています。たとえば、エンジニアとデザイナーが協働することで、技術と感性が融合したプロダクトが生まれる。若手社員とベテラン社員が対話することで、過去の知見と新しい視点が交わり、思いもよらないアイディアが生まれる。異なる視点が交わることで、問いが深まり、解決策の幅が広がる。
それが、共創の力です。
<実例:多様性が拓いた共創の成果>
・富士通では、社内の多様な人材が参加する「デザイン思考ワークショップ」で新規事業が生まれています。部署や職種を超えた対話が、顧客視点のサービス開発につながっています。
・資生堂は、国籍・性別・職種の違いを活かし、グローバル市場に通用する商品開発を実現。多様なチーム構成が、世界中の顧客ニーズに応える力になっています。
・スタートアップ企業では、顧客との共創によって、製品の改善スピードと満足度が劇的に向上。β版のフィードバックをもとに、ユーザーと一緒にプロダクトを育てる文化が根付いています。
これらの事例に共通するのは、「違いを活かす交流の場」が意図的に設計されている点です。
共創を促すチーム・組織の設計
では、どうすれば共創が生まれるチームや関係性を育てられるのでしょうか?
その鍵は、企業の枠内に閉じた設計ではなく、広範なステークホルダー――顧客や市民、外部パートナーなど――も含めた双方向で自発的な“交流”にあります。従来のような企業側が一方的に行う「調査・分析・フィードバック取得」といった確立的アプローチだけでなく、関係性そのものを育てることが求められます。
以下の3つの要素は、そうした共創を設計するうえでの出発点です:
心理的安全性:誰もが安心して意見を言える環境づくり。否定や嘲笑のない受容的な環境。
目的の共有:共通のゴールを持つことで、多様性が力に変わります。方向性がバラバラでは共創は起こりません。
対話の場:部署横断の勉強会や顧客とのワークショップなど、立場を越えて話し合える場を意図的に設計すること。
共創とは、偶然ではなく“設計”するもの。そしてその設計は、「違いを受け入れる姿勢」と「つながりを育む仕組み」があって初めて機能します。
10 Inc.の取り組み:インナーとアウターの両輪での共創
現在10 Inc.では、インナーブランディングの一環として「つながりを育む仕組み」を設計し、組織のあり方を再構築しています。
また、コンサルテーションサービスではクライアント企業と生活者が“交流”し、関係性を築きながら共に価値を見出すプロセスを重視。私たちはそのパートナーとして、対話・共感・創造のプロセスを伴走型で支援しています。
こうしたインナーとアウター、両側から共創を体現していくこと。それが私たちの掲げる理想の姿です。
おわりに:共創の未来へ──関係性を力に変える
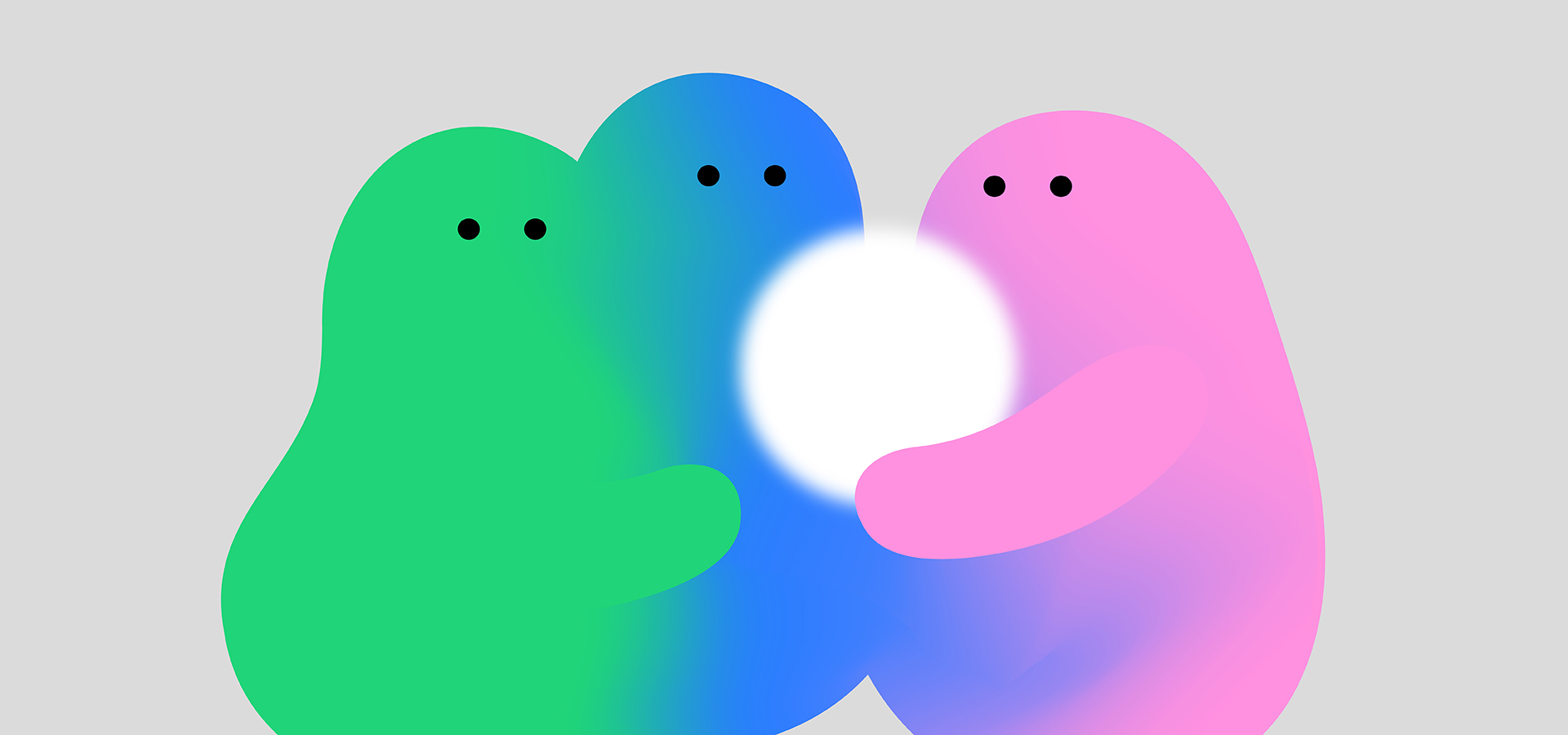
「異なるからこそ、つながれる」──この言葉は、決して理想論ではありません。
共創は、企業が単独で完結する活動ではなく、顧客を含む多様な主体との“関係性”から始まる営みです。違いを受け入れ、共に問い、共に進む。そのプロセスそのものが、新しい価値を生み出します。
違いを活かし、関係性を育む――それが、これからの価値創出の鍵となるのです。
参考情報
富士通グループ CSRレポート/共創イニシアチブ、資生堂グループ サステナビリティサイト、SmartHR公式ブログ/SmartHR NEXT、BASE Developers Blog、Notion公式コミュニティサイト、『エアビーアンドビー ストーリー』(著:リー・ギャラガー)、Ubie公式ブログ など
次回のコラムは、「AI×価値共創」をテーマに発信したいと思います。
日々進歩している生成AI。これからの未来のビジネスにおいて100%共存するAIですが、私たちヒトがイニシアティブを持ってAIと価値共創をどのように推進していくべきかを考えたいと思います。




